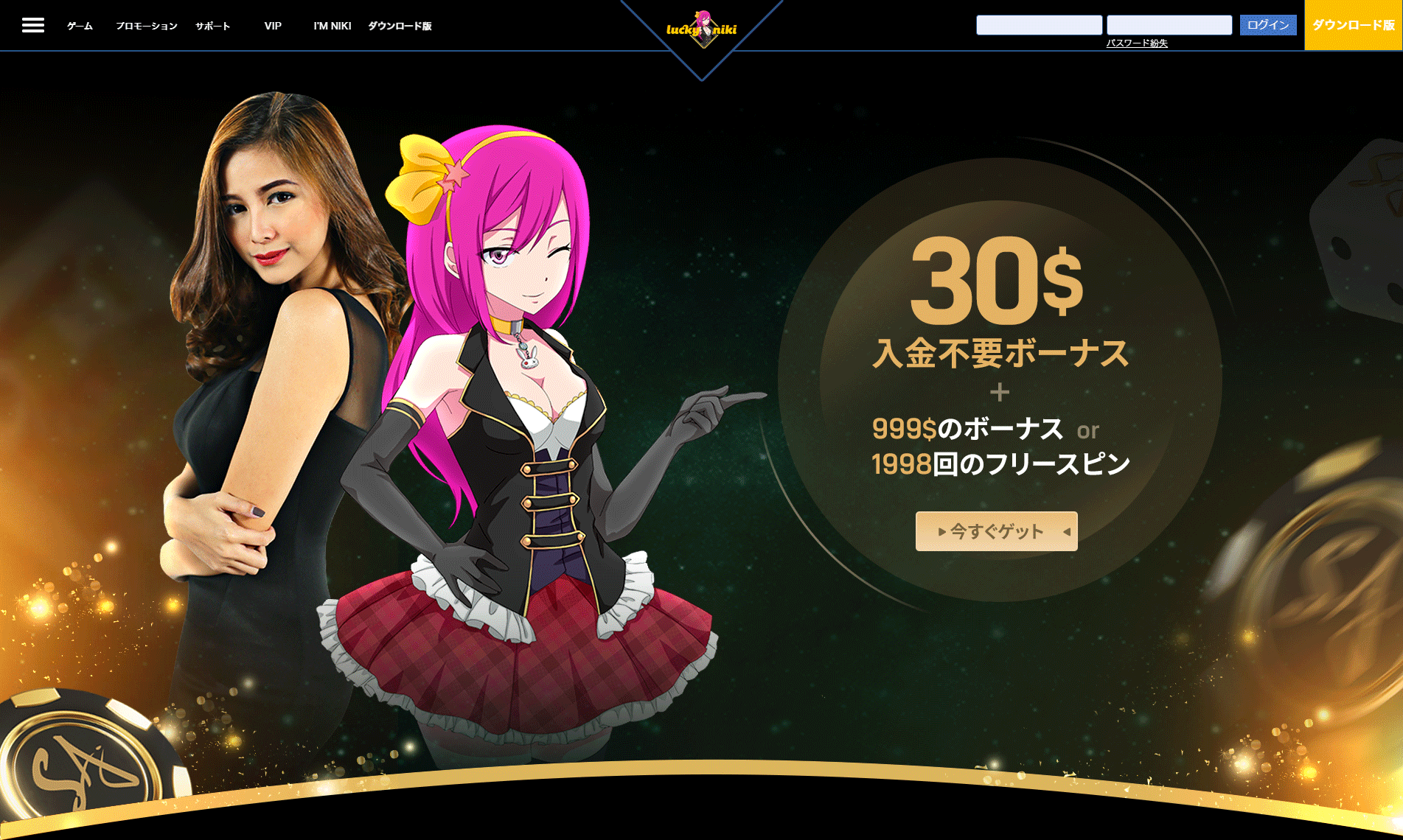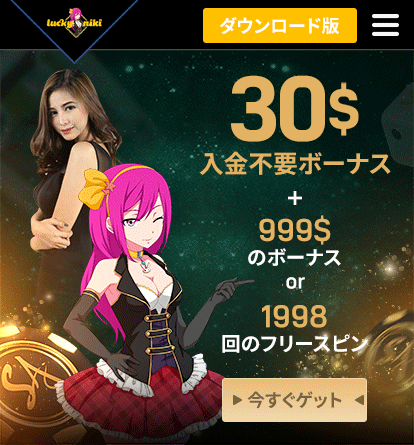米軍基地建設計画
現在、尖閣諸島に米軍基地を作る計画が進行しているそうです。
アメリカ陸軍長官のライアン・マッカーシーが公式のインタビューの中で、2021年に新たな米軍基地を尖閣諸島に作ることを検討していると述べました。
アメリカのCIAが1971年に作成した極秘レポートには【尖閣諸島が日本のものである、という日本の主張は強く説得力がある。】と書かれていました。
ようするに、アメリカは尖閣諸島は日本の領土であると認識しているようです。
現在まで中国は尖閣諸島に何度も侵入しています。
もし尖閣諸島に米軍基地が運用されるようになれば、今までのように好き勝手に侵入されることはなくなるかもしれません。
尖閣諸島の歴史

尖閣諸島は沖縄県石垣島の北西130km~150kmにある、5つの島と岩礁です。
尖閣諸島は琉球王国から中国への航路上にあり、その存在は古くから琉球王国で知られていました。
住んでいたのは、日本人です。
むかしは琉球人が航海の目印として利用する程度で、人の住む地から遠く離れていたので、漁に来ても魚が腐ってしまうので魚を持ち帰ることができず、島そのものにも利用価値は無く漁に来たり上陸し住む人は、いませんでした。
その後、1884年に古賀辰四郎という日本人の探検家が尖閣諸島に降り立ち、ここを拠点に事業を始めたいと考えました。
古賀が日本政府に対して尖閣諸島を事業の拠点として使えないか申請した際、日本政府は、尖閣諸島がどこの国にも属していないことを確認した上で、1985年に日本領へ編入しました。
そして約200名の日本人が居住しアホウドリの羽毛の採取などの事業を始めました。
これが尖閣諸島への最初の居住になりました。
最初は事業の方もうまくいっていましたが、次第に経営がくるしくなり、また太平洋戦争により米軍が沖縄侵攻の可能性があったことから、1940年以降は、全ての島が無人島になってしまいました。
1945年第二次世界大戦に負けた日本は、それまでに領有していた国土を中国と台湾に返還するようにもとめられました。
しかし、返還を求められた際に尖閣諸島はその中に含まれていませんでした。
それから先は、尖閣諸島はアメリカの軍事支配下に置かれることになります。
その後、1972年に沖縄返還協定が発効され、尖閣諸島は日本に返還されることになりました。
尖閣諸島にある大正島と久場島は、アメリカ軍の射撃場として使うようになり、現在に至っいます。
尖閣諸島問題の始まり
尖閣諸島問題の始まりは、1968年の海底調査の結果、東シナ海の大陸棚に石油資源が埋蔵されている可能性があることが判明し、1970年に台湾が領有権を主張しはじめ、これに中国も追随した。
1970年に国連が行った海洋調査では、推定1086億バレルという、イラクの埋蔵量に匹敵する大量の石油埋蔵量の可能性が報告された。
1970年以降から中国が、尖閣諸島は中国のものであるという主張を始めたのです。
対して日本政府は国際法上、先占の法理に基づいて、尖閣諸島が日本の領土であると主張しています。
先占の法理上、1占有の対象が無主の土地である、2国家による占有である、3実行的な支配がある、この3つを満たしていれば、国際法上日本のものであると言えます。
尖閣諸島は江戸時代から貿易に使うための目印の島として認識されていたものの、どの国の領土でもありませんでした。
そのことから、1の占有の対象が無主の土地であることを満たしています。
1895年、尖閣諸島は正式に日本領へ編入され、日本政府が貸し出した土地を使用して古賀辰四郎や日本人が事業を始めたことで2と3の国家による占有である、実行的な支配があるも満たすことができます。
対して中国政府は、1534年に冊封使の陳侃が琉球に向かう際、尖閣諸島を発見し中国語の名前で公式な書類に記載したことを挙げ、先に中国が発見したと主張しています。
また、地理的にも中国の方が近いことも挙げています。

しかし中国が主張している陳侃の記録は、尖閣諸島が中国領であったとする証拠にはなりません。
国際法上、先に発見したことや地理的に近いことは領有権とは関係のないことです。
また、中国が尖閣諸島を先に発見したという証拠もありません。
尖閣諸島の問題はとてもセンシティブな問題なのですぐに解決するというのは難しいかもしれません。
まとめ
日本もアメリカの安全保障条約に頼らず、ある程度の軍備拡張と憲法改正をしなければ中国のような挑発国に好き放題にされます。
現在のアメリカのトランプ大統領は、安全保障条約により日本の領土を守ると言っていますが、前任のオバマ大統領は中立の立場でした、今年のアメリカ大統領選挙でどのような展開になるかわかりません。
日本のメディアは、中国に遠慮して中国問題をあまり報道しません。
この記事を読んでいただいた方は、この機会に日本の実態を理解していただいて、考えていただく機会になればと思います。